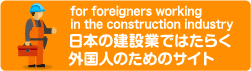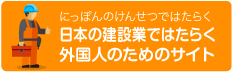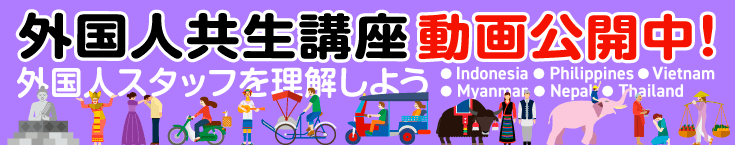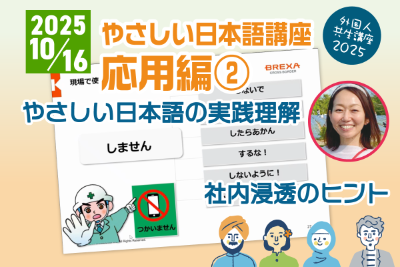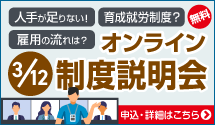- やさしい日本語
- ひらがなをつける
- Language
機械翻訳による多言語コンテンツを提供しています。翻訳精度は100%ではありません。JAC Webサイトの多言語化について
- JACについて
- JAC入会案内
- 特定技能外国人受入れ
- 受入支援サービス
- 特定技能受入支援サービス
- スキルアップ支援
- オンライン特別教育
- 技能講習
- 日本語講座
- 教育訓練支援
- 資格取得等奨励金制度
- 働きやすい職場づくり支援
- 一時帰国支援
- CCUS手数料支援
- 就労履歴蓄積等促進支援制度
- 受入れ後講習
- 1号特定技能外国人向け補償制度
- 日常生活サポート
- 医療通訳サポート
- 生活トラブルサポート
- 無料求人求職
- 特定技能評価試験
- ホーム
- JACマガジン
- 外国人労働者との働きかた
- 外国人が混乱する日本語・外国人に伝わらない日本語とは?
- ホーム
- JACマガジン
- 外国人労働者との働きかた
- 外国人が混乱する日本語・外国人に伝わらない日本語とは?

外国人が混乱する日本語・外国人に伝わらない日本語とは?
私が記事を書きました!

(一社)建設技能人材機構(JAC)
調査研究部 主任 / 管理部 / 広報部
加納 素子
(かのう もとこ)

こんにちは、JAC(建設技能人材機構)の加納です。
日本語が母国語ではない外国人にとって、日本語は非常に難しい言語です。
外国人と接する機会が多い方の中には、「わかりやすく話しているつもりなのに、なぜか伝わらない」といったお悩みをお持ちの方もいるかもしれません。
実は、日本人が何気なく使っている表現も外国人には伝わりづらいケースが多いです。
今回は、外国人が混乱する日本語や、外国人に伝わらない日本語をご紹介します。
わかりやすく伝えるポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
外国人が混乱する日本語・外国人に伝わらない日本語とは?
外国人が混乱する日本語や、外国人に伝わらない日本語はいくつかあります。
代表的なのは、以下のようなものです。
- 長文
- 同音異義語
- オノマトペ
- 主語や目的語がない文章
- YES・NOがはっきりしていない表現
- 尊敬語・謙譲語
- ため口
- 外来語・和製英語(カタカナ)
- 略語
- 方言
- 二重否定
次で、例文を交えながら詳しく解説します。
【例文】外国人が混乱する日本語・外国人に伝わらない日本語

外国人が混乱する日本語や、外国人に伝わらない日本語について、例文も交えて解説します。
長文
一文が長すぎたり、一つの文章の中にいくつも情報が入っていたりすると、理解が難しいです。
不要な情報は取り除き、一文を短くして伝えます。
【例】
現場で予定外の不具合が見つかったので修正が必要になり、その影響で14:00に予定されていた材料の搬入時間も変更しなければなりません。
→現場で配管に不具合が見つかりました。その配管の修理が必要です。材料の搬入は、配管の修理が終わってからやります。
同音異義語
「機会(KIKAI)」と「機械(KIKAI)」、「性格(SEIKAKU)」と「正確(SEIKAKU)」など、読み方は同じなのに、漢字と意味が異なるものを同音異義語と言います。
アクセントの置き方を工夫するだけでは、外国人に伝わりづらい言葉です。
別の言葉で表現できるときは、言い換えをするとわかりやすいです。
【例】
また次の機会に、一緒に食事をしましょう。
→次に会うときには、一緒に食事をしましょう。
オノマトペ
「ずきずき(ZUKIZUKI)」「がんがん(GANGAN)」「バタバタ(BATABATA)」など、音や状態を表現する言葉をオノマトペと言います。
例えば犬の鳴き声は、日本では「ワンワン(WANWAN)」ですが、英語では「バウワウ(BOWWOW)」と表現します。
各言語に独自のオノマトペが存在するため、オノマトペは使わないほうが伝わりやすいです。
【例】
頭がずきずきする。
→頭が痛いです。
ただし、痛みの表現のオノマトペは知っておくと万が一の際に役に立ちます。
日本語に慣れてきたら、覚えてもらうと良いでしょう。
痛みの表現については、こちらで詳しく解説しています。
日本語の「痛みの表現」を知ろう!うまく痛みを伝える方法も
また、外国人が痛みを訴えている場合は、痛みのレベルを数字で聞くと状況を判断しやすくなります。
「痛みの強さを0から10の数字で答えてください」などと聞いてみましょう。
主語や目的語がない文章
外国人は、主語や述語、目的語が揃っていない文章を理解するのが難しいです。
【例】
今晩、どう?(飲み物を飲むジェスチャーをしながら)
→あなたは、今日の夜、一緒に食事に行きますか?
YES・NOがはっきりしない表現
YES・NOがはっきりしない、あいまいな表現は伝わりません。
【例】
結構です。
→いりません。
【例】
今度にしましょう。(「今日一緒にランチに行きませんか?」という誘いに対して)
→今日は、私は行けません。
尊敬語・謙譲語
「していらっしゃる」などの尊敬語や、「申し上げます」などの謙譲語は外国人には難しいです。
【例】
お客様がいらっしゃいます。
→お客様が来ます。
ため口
実はため口も、外国人には伝わりにくい日本語です。
外国人が日本語を学ぶときは、文末が「です(desu)」「ます(masu)」といった丁寧語で学ぶので、それに合わせた表現にすると良いでしょう。
【例】
ハンマー持ってきて。
→ハンマーを持ってきてください。
外来語・和製英語(カタカナ)
カタカナで表す外来語は、外国から入ってきた言葉の発音をそのまま日本語読みにしたものです。
例えば食事の「パン(PAN)」はよく使われますが、元々はポルトガル語なので、英語圏の人には伝わりません。
英語圏の人の場合、「パン=調理器具のフライパン」と伝わる可能性があります。
英語由来の言葉でも「コーヒー(KŌHĪ)」は英語の発音では「カフェ(KAFE)」に近いため、カタカナでは正しく伝わらないことがあります。
また、 同じくカタカナで表す和製英語は、英単語の意味やニュアンスを解釈して、日本人が英語のように作り上げた言葉です。
そのため、外国人に伝わらないものも多いです。
【例】
- 外来語:パン、コーヒー、アルバイト、コップ など
- 和製英語:ホチキス(stapler)、ノートパソコン(laptop) など
略語
日本語を省略した略語は元の言葉がわからなくなるので、正式名称で伝えるようにします。
【例】
有給
→有給休暇
また、日本では英語由来の言葉の省略が多く、外国人にとっては理解できないケースも多々あります。
【例】
パソコン(personal computer)、リモコン(remote control)、ファミレス(family restaurant)
方言
標準語で日本語を学ぶ外国人にとって、言葉そのものが変わってしまう方言は難しいです。
【例】
おらん。
→人がいません。
二重否定
否定の言葉を重ねて肯定の意味を伝えたり、肯定をあいまいに伝えたいときに使う二重表現は難しいので、シンプルな言葉や文章に直します。
【例】
行かないわけではない。
→行きます。
外国人にわかりやすい日本語にするポイント
外国人にわかりやすい日本語にするためには、ポイントがあります。
次のようなポイントを押さえると、外国人も理解しやすいです。
- ジェスチャーを使う
- 結論は最初に言う
- 反応を見ながら適度なスピードで話す
- 短い文章で伝える
- あいまいな表現は使わず、はっきりと言いきる
話して伝える場合は、外国人の反応を見ながら伝わり方をチェックしましょう。
ジェスチャーも入れることで、理解度が上がります。
日本語を書いて伝える場合には、次のようなポイントも意識しましょう。
- 漢字をたくさん使わない
- 漢字にはふりがなを付ける
- 絵や写真、図を積極的に入れる
漢字は外国人にとっては難しいので、ふりがなを付けましょう。
また、絵や写真などの視覚的な情報も取り入れることで理解が進みます。
難しく感じるかもしれませんが、人と人とのコミュニケーションなので、会話をしながら積極的に関わっていくことも大切です。
外国人にわかりやすい日本語として、日本では「やさしい日本語」というものがあります。
主に災害情報や役所の案内等で使われており、日本語が得意ではない外国人向けの情報発信に役立っています。
やさしい日本語については、こちらで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
やさしい日本語とは?例文や生まれた経緯などを紹介
まとめ:外国人が混乱する日本語・外国人に伝わらない日本語は多い
普段、日本人が普段使っている日本語には、外国人にとっては伝わりにくい表現も多いです。
特に日本人は、はっきりと結論を言わなかったり、端的に答えずにあいまいな表現にしたりすることも多く、外国人には理解が難しいです。
外国人に伝わりやすい日本語は、主語、述語などの文法が整っていて、「です(desu)」「ます(masu)」などで終わる丁寧語の文です。
また、カタカナで書かれる外来語や和製英語は、日本独特の言葉になっているものが多いので、できるだけ使わないよう注意しましょう。
「ずきずき(ZUKIZUKI)」などのオノマトペも外国人にはなかなか伝わらない日本語です。
しかし、状態や気持ちを表現しやすい言葉なので、徐々に覚えてもらうのも良いでしょう。
外国人により伝わりやすくするためには、ジェスチャーを取り入れるなどの工夫も大切です。
コミュニケーションを取りながら、その外国人に合った話し方や表現を見つけていきましょう。
建設業界で特定技能外国人の受入れをお考えの企業様は、JACにお気軽にご相談ください!
特定技能外国人のご紹介も行っております。
この記事を書いた人